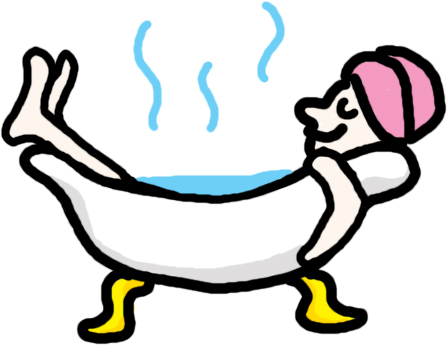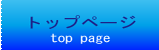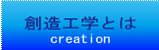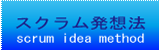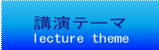第6章 創造工学、創造技法
創造する機能を工学として、法として捉えてみよう。
ピンチになると生命を助ける為にアイデアをだす脳の働きは、どのような仕組みになっているのだろう。
テーマXに対してヒントYを右脳に蓄積されているイメージデータを走査、スキャニングして役に立つデータを見つける。
この見つける脳はどんな働きをしているのでしょう。
直観とはどんな働きをしているのでしょう。
そのメカニズムを解明したのが中山正和先生です。
その方法を名前の頭文字よりNM法と呼びます。
1.テーマXとヒントYとの関係、Analogy ?
テーマXの解決に役に立つデータYを右脳より走査して見つける機能。
プログラムは一つ、Analogy(似たもの、類比、類似)の関係にある。
2.Analogyの例
(1) ヘリコプター と ヒント 竹とんぼ
(2) レーダ と ヒント 蝙蝠(こうもり)
(3) タイヤ と ヒント サッカーボール
(4) 新幹線の消音装置 と ヒント しま梟(ふくろう)
3.NM法のステップ
(1) KW・・・Key Word の略
テーマを抽象化する。
動詞又は形容詞で
(2) QA・・・Question Analogy
例えば○○のように。
図解せよ。
(3) QB・・・Question Buckground
そこでは何が起きているか。
(4) QC・・・Question Conception
着想、ヒント。
それが(QB)テーマの解決に何か役にたたないか、又は暗示してないか。
(5) QD・・・Question Abuduction
QCで数多く出て来たヒントの中より光るものを選出し、更に組み合わせ、練り上げていく。